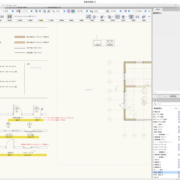左:Tofuku Daisuke 零三工作室 右:山上健 山上建築設計
Prev:BIMが切り開く新たな創造性 第5回〜 村井一建築設計/東京大学生産技術研究所 特任助教 村井一氏インタビュー〜
JIA東海支部機関紙ARCHITECT連動連載企画
BIMが切り開く新たな創造性 第6回(最終回)〜零三工作室 東福大輔、山上建築設計 山上健 座談会〜
スタンズアーキテクツ株式会社/株式会社フローワークス 代表 横関 浩
BIMが切り開く新たな創造性 第6回は、零三工作室 東福大輔氏、山上建築設計 山上健氏を迎えBIMと創造性に関する座談会の内容をお伝えします。
目次
1、BIMが建築に何をもたらしたのか。
2、BIMが建築をどう進化させるのか。
3、創造性をどう生み出していくのか。
4、社会とどう接続させるのか。
<自己紹介>
横関:今日はBIMが切り開く新たな創造性について座談会を行いたいと思います。ではまず自己紹介から。東福さんからお願いします。
東福:東福大輔と申します。名古屋大学の大学院を卒業した後、鹿島建設に7年弱勤めました。その後、磯崎新アトリエに入り、5年弱勤めました。磯崎さんのところでは中国で美術館をほぼ一人で監理していました。その後、中国で設計事務所を立ち上げ、全部合わせて約10年間中国に滞在し、その経験は著作にまとめています。当時、北京オリンピックで多くの設計事務所が集まっていて、世界各地の設計事務所との交流があり、非常に面白い時期でした。
ただ、中国では疲れることが多く、約8年前に日本に帰国しました。帰国後、笠寺観音のプロジェクトを手がけることができました。そしてBIMをそろそろ始めなければならないと考え、現在は山上さんと一緒に別のプロジェクトを手がけています。あと、ライノセラスとグラスホッパーを大学で非常勤講師として教えています。
横関:ありがとうございます。では、山上さん、よろしくお願いいたします。
山上:山上建築設計の山上健です、よろしくお願いします。名古屋大学出身で、僕が学部1年生の時、ちょうど恒川先生が名大で教え始められました。大学を出て、少しだけRIAに勤めてから、名古屋の伊藤建築設計事務所という所で修行しました。その伊藤に在籍中にですね、2008年とか7年とかにArchicadというBIMソフトを使い始めました。2~3年使ってみて、「これはいけるぞ」となって、2011年1月からArchicad一本に絞ってやっています。
人よりも早い時期からArchicadを使っていたので、グラフィソフトから声が掛かって、Archicadを実際に使っている事例の紹介などで全国を回っているうちに、グラフィソフトの認定コンサルタントという立場になりました。認定コンサルタントは全国で20人くらいいると思いますが、中部では僕一人です。あとグラフィソフトのスクールの講師をやっていて、これはWEBなので全国の人を教えています。一応、BIMコンサルティングみたいなこともやっています。他には東福さんのお仕事をお手伝いしたりもしています。
横関:ありがとうございます。
1、BIMが建築に何をもたらしたのか。
横関:では、まずBIMが建築に何をもたらしたのかというところをお話しいただければと思います。では、お願いします。
山上:設計者にストレスとプレッシャーをもたらしました。(笑)
東福:そう。いずれそういったストレスは減っていく方向に開発はされていくのでしょうけど、なんでこんな簡単なことがこんな大変になってしまうのかという疑問が湧いてくるアプリですね。海外で生まれたBIMやCADを日本に持ってくるときに、日本の事情に合わせてローカライズをしなくてはならない。それは大変な作業だと思います。それを抜きにして考えると、日本でいえば、BIMが教育現場等で使われたり、新人教育で使われると一番変わるであろうことは、構法に対する知識じゃないかなと思ってます。 要は大学卒業して会社に入ってしばらく経つまで、LGS下地に石こうボードを貼るなんて知らないわけじゃないですか。レムコールハースも「LGSが建築史で軽視されている」みたいなことを言っていたと思いますけれど、空間を作る上では、実際にはRCよりもLGSの方が圧倒的に多いわけです。でも、日本では、建築教育ではあんまりやらないんですね。構法教育を充実させないことの良さっていうのが、日本の建築教育の良さなのかもしれませんが、やはりその圧は増していくんじゃないかなということは予想できます。
横関:そうするとBIMが建築にもたらしうるものの一つが、教育に構法を持ち込むことだと。
東福:要はプロとしてトレーニングを受けるというのは構法を覚えるってことで、それを先行して教えるっていうか習得するようなことが起こるんじゃないかなと。
横関:なるほど。BIMは建築情報が付いた立体データを持つようになる。グラスホッパーなどの自動生成を行うようなものと相性がよくなってくれそうです。その辺りから建築にもたらしそうなものはありますか。
東福:色々実験はしているんですけどね。BIMのデータを書き出す方法がまだよく分かってない。彫刻とかそういうような建物の中にあるオブジェクトレベルだったら十分できますね。
横関:自動化させるプログラムとBIMをどう連結させるのか。そこがまだ弱くて上手く使えていない。
東福:そうですね。それができるのはVisualARQ2しかなくて。それを持っている人は僕は一人くらいしか知らないんですよね。その人も使ってない感じなので、おそらくVisualARQ2は日本の建築事情にまだローカライズされていない。そうするとみんなやっぱり使わなくなっちゃう。そういうようなデータの連携がうまくいくようになればもっとできると思うし、もっと普及していいよねといつも思っています。
横関:ありがとうございます。では、話を広げましょうか。
山上:東福さんは教育に構法がもたらされるとおっしゃいましたけど、僕はそうはならないような気もします。確かにBIMソフトは構法と相性が良いのですが、大学の教育としてはこのままいくんじゃないかなって。例えば僕も大学でもBIMを教えてるんですけど、そこで期待されているのは3Dのモデルを作ってパースを作って基本設計図を作って、というところまでです。そもそも僕自身、大学って本質的にはBIM教育って要らないかなと思ってて。
横関:そのあたり詳しく教えてください。
山上:東福さんはライノやグラスホッパーを教えていますよね。そっちでいいじゃんって思ってて、構法よりも、今の大学の教育を肯定しているというか。例えば早稲田とかだと絶対実務からって校風がありますけど、少なくとも僕がいた頃は名古屋大学はそういう校風ではなかった。名古屋大学の良いところと悪いところとを色々と考えてみると、構法とかじゃなくて、建築の概念的なところを教えてもらったっていうのは良かったかなと思ってます。
東福:僕もそう思っているけれど、むしろ僕が言いたいのはBIMっていうのは構法を教えるツールとして教えないと意味がないというところ。
山上:そうですね。もし構法とセットで扱うのなら、BIMを大学で教える意義もあると思います。
東福:私が大学に居たころ、構法の授業は正直ひどかったんですよね。絶対構法の知識ない先生が教えていた。だからこそ、BIMを教えたいのならば構法の授業と組み合わせるべきだと言ってるんですよね。
山上:その話は以前から東福さんと何度かしてきて、僕も同意してきたんですけど、よくよく考えたらちょっと違ったなと最近思って。そもそもBIMっていう言葉が今めちゃくちゃいろんな意味で使われるので、BIMソフトのことをBIMって言ってるのか、それともその先にあるすべての世界をBIMって言っているのかグッチャグチャじゃないですか。 で、今東福さんがおっしゃったのはBIMソフトの話なんですよね。BIMソフトと構法をセットで扱うべきということには以前と変わらず同意なんですけど、ソフトの使い方とかじゃなく、BIMという言葉が示している未来の世界の考え方とかを知るのなら、構法とセットにしなくてもいいかなと最近は思うようになってきました。つまり、今行われているような形でBIMソフトの使い方を大学で教える必要はなくて、構法とセットなら意味はある。それとは別の観点で、ソフトの操作方法ではないBIMの広範な概念を教えるのであれば、大学で教える意味はあるかも知れない。
横関:建築の設計では、コンセプトを組み立ててそれを実現するプロセスを踏みます。東福さんはBIMでやることによってその後半の知識が、教育に前倒しされていくというようなイメージをされている。逆に山上さんは、実現化に進んで行くに決まっているので、大学教育では前半に重心を置いて教育をするべきだというようなイメージ。その辺どうでしょうか。
山上:やっぱり大学の教育の大事なところって、設計事務所に入ってから教えてもらえないこと、良い設計事務所、例えば、組織事務所やアトリエとかで、トップレベルの本当にトップの人たちとかに、教えられるような概念的なことというのは、普通の事務所で教えてもらえないですよね。 RIAに入って結構期待したんですけど、あんまりそういうことは出てこなくて、大学で先生に言われたようなことって、誰も言わない。やっぱりそういうことは大学で教えなきゃいけないなって思ったんですよね。そっちに時間を割くほうがいいなと思って。 BIMっていうのは設計を考えるツールじゃないと思ってます。考えるのはまだやっぱりライノセラスとかグラスホッパーの方がいい。だから大学生はそっちやっていればいいじゃんって僕は思ってるんです。 BIMはさっきグッチャグチャって言いましたけど、そもそもBIMってあんまり定義できないものなんですね。だってコンピューターで建物の情報がデジタルになってるだけの話ならBIMソフトの話なんですよ。でもBIMっていう概念は、それ自体はもうなんかプラットフォームとかインフラみたいなもので、「BIMだから何、じゃあどこまでBIMなの」という話じゃないですか。 この連載の杉田さんのお話の中でで、建築のデジタル化なのかBIMなのかよく分からないみたいな件がありましたけれど、まさにそうなんですよね。BIMっていう言葉が今本当にふわふわしてて、狭義にはBIMソフトだけのことを指して使われていますが、広義にはもっとずっと広い概念としても使われていて。だから「BIMだからどうこう」って言われてもよくわからない。正直話しにくい。
横関:では、何か建築が変わったと実感するものがあるとしたら、BIMのどの部分がそれをもたらしたと言えますでしょうか。
ARCHITECT掲載ここまで。
山上:とりあえずこの特集を4回分読ませていただいたんですけど、もう全部同意ですね。お互いにバッティングしてることも多分言ってると思うんですけど、基本的に全部同意です。BIMがもたらしたものってのは多々あると思います。
横関:BIMはある意味、誰にでもなんらかの変化をもたらす?
山上:そうですね。この人たちだけじゃなくて、電脳設計論壇の中で話された方たちとか、全国にいるArchiCADを教えた人とか、ユーザーグループとか、いろんな人と話をすると、やっぱりよく使ってる人ってみんなおんなじような感覚を持っているんですよね。ただ、やっぱりまだこれからっていう感覚が大きい。そういう意味で可能性に満ち満ちていて、現時点で何をもたらしたかというと、、、
東福:ストレスですね。(笑)
山上:僕はないですけど。多分いろんな人がストレスを抱えてますよね。
横関:それ以外のところでは?
山上:まずやっぱり形についてはだいぶ自由になったなと思います。BIMというか、ライノセラスとかも含めて。これまで表現できなかったこととか、頭の中で考えてスケッチを描いてもやっぱり立体にはならないので、それが全部ちゃんと正確な形として認識できるようになったのは大きいって思います。あと、このコンピューターの力を使って何万回も試行ができるってことですよね。
山上:その中から良いものを選び取れるという新しいスタイルが出てきたのは確かです。
横関:分かりました。言い換えれば、BIMというものは一つの要素。そういうものはあるかもしれないけれども、デジタル設計という大きな枠の中で考えれば、建築に1種の自由度というのが与えられてきているというのは間違いないと言えますかね。
山上:大きく言えば間違いなくそうだと思ってます
横関:逆に言うと、BIMで括るよりも、もっと大きな視点で見た方がいいよと。
山上:そうですね。BIMが多分その大きな視点なんでしょうけど、それって何か僕は気持ち悪いんですよね。それをBIMって言うのか。
横関:なるほど。分かりました。
2、BIMが建築をどう進化させるのか。
横関:いろいろお話に出たBIMの良いところも悪いところもあったと思います。私自身はBIMというのはこの新しいデジタル設計のコア技術だと思っているのですが、それがあることでコンピュータが建物を理解できるように立体データに建築データが付いて、シミュレーションができるじゃないですか。つまり、それをベースにしてGRASSHOPPERなどいろいろなものができてきて、デジタル設計全体というのが構築されると考えていますが、そこまで含めて、そういうものが今後建築をどう進化させるのか。もちろん GRASSHOPPERなどやられているので、もうかなりチャレンジングなことされていると思うのですが、同時にいまいち使われていないというお話もありましたよね。
東福:BIM化ですね。
横関:はい、そうですね。そこで、このBIMもしくはそのデジタル設計が建築をどう進化させていくかというところについて、ちょっと議論したいと思います。可能性のところをちょっとお話しできますでしょうか。
東福:技術的な話ですかね。そのGRASSHOPPERみたいなデジタルファブリケーションはまた別の次元としてあると思うのですが、いわゆるデジタルのプログラミング的なシェイプの操作、形態操作的な。
横関:コンピュテーショナルデザイン。
東福:そうですね、コンピューテショナルデザインということで、今一番流行っているというか一番注目されているのはやっぱり環境対応ですよね。音であるとか温熱環境であるとか風であるとか、そこら辺を制御する形みたいなものを探求する部分もあるし、実際、川島 範久さんの「環境シミュレーション建築デザイン実践ガイドブック」は第3版が出ている。
私も音で形を作ったことがあるので、そういうような話というのは一番わかりやすいですし、お客さんも納得いしやすい。変な形にしてもこれはコンピュータに計算させたんですとある種のブラフというか、そういったことができるということですよね。もちろんクリエイションの話ではもっといろんなことが当然できます。
横関:つまりそれは建築をどう進化させたと?
東福:進化させたのかどうか微妙だと思うけど、やっぱりある種のブラックボックス的なものを用意して、これは音響的に良いんですよというようなことが言えるようになったというのは大きいですよね。お客さんも設計者側も実は本当にわかっているのか怪しいところで、でも形は面白いから良いよね。私のやっているのもやっぱり一番格好いいところは止めるように、そういう結果が出るようにパラメーターを制御していろいろやっているんですよね。それはもう誰でもそうだと思いますね、多分コンピュータを使う人は、コンピュータをある種設計の、、、、
山上:根拠ですね。
東福:根拠?でもブラッフィングだよね、基本的には。
山上:それを根拠とみんな言っているんです。
東福:そう言われてもおかしくないようなことをやっている人が多い状況ですね。
横関:ありがとうございます。今まで何となく設計者の勘であるとか、要は感覚的なところなんですよね。そういうものがある程度可視化できるようになったところが大きいってい。後もう一つ。この後の創造性というところに結びついていくのですが、一番格好いいところで止めるとおっしゃていた部分。
東福:はい。
横関:そこの部分が建築を進化させるんじゃないかと。今まで建築家とか設計者の方々が一番自分がいいと思っていたところが更に引き上がる。それは先程山上さんも言われましたが、たくさんのシミュレーションを行えるとか、いろんな自動生成したもので見て確認できるという風になると、今まで10個の中から選んでいたのが百個、一万個の中から選べるとなると変わってくるじゃないですか。
東福:自動生成の良さはそれですよね。スタディーが無限にできる。
山上:日本の国交省がやってるのはどっちかってイギリスとかヨーロッパを参考にしていて、あっちの方だと建築設計者の立場というか役割がが変わってきていると。仕事としてはBIMマネージャーっていう仕事が出てきている、役職として。欧米でちっちゃな事務所だと日本みたいな一人で設計をやっている人は全部自分でやりますけども、もう少し大きくなると組織をマネージメントする人とデザイナーと二大巨頭がいて、その設計事務所が成り立っているっていうスタイルがあったところに更に横並びでBIMマネージャーが加わるという状況が今出てきているという話があって、その人は何をするかって設計事務所の中のワークフローをやるんですけど、クライアントさんとかあるいは施工者さんのところのやり取りにも関わってくると。でも、チームの作り方も元々設計・施工で分かれていたのが日本のデザインビルドみたいな仕組みで仕事を始める、そういう形態も出てきているとか、いろんな仕事のやり方の形が変わってきているんですね。クライエント側にもBIMマネージャーが必要になってきていて、今だと役所とか大きい鉄道会社とか、そういうところは自分達が設計するわけじゃないけど、 BIMマネージャーを仕事としても募集してるんですね。
横関:面白いですね。
山上:という状況があって、当然大手の設計事務所の人は日本でもそういう情報をキャッチしているので、設計事務所の仕事としてこれからBIMマネージャーというのも仕事としてやっていこうとしている。で、大手のクライアントがどういうふうにBIMの案件を発注したらいいかっていうのをコンサルティングの仕事にしようとしているんですね。だからBIMっていうもので、その設計者が社会とかクライアントさんとかにどう関わっていくかというその関わり方自体がちょっと変わってくる。だからもっと川上から始まっていけるし、というのが設計者なんですけど、結局企画段階で東福さんがおしゃったみたいに、いろいろブラフをかます人が出てきたら、もっと多分、早い段階で意見していけると思うんですよね。でもうちょっといい言い方をすると、設計者のいい部分というのが活かせるんじゃないかなっていう可能性はあるんじゃないかなって思います。要は設計者って視点が大事じゃないですか。それが早い段階からプロジェクトの中に視点を投入していけるという可能性はあるのかなと思っています。それは結果的にできあがる建築にもいい影響を及ぼすという可能性はあるかなと。
横関:設計のプロセスがやはり大きく変わってきた。それとクライアント側にもそういう知識を求められ始めている。
山上:国交省もそういうスキームで今このBIM建築をやってますし、それは欧米の人がそう言ってるからそうやってるんですけど、ただ、それが本当に必要かどうかもわからないですし、日本で。
東福:シンガポールとかだったらわかるよ。シンガポールはね、コンペとかでIFCで託さなきゃいけないとか決まりがあるじゃないですか。そういうようなものだったら結構大きな建物が建つものだったら、それは行政側にもBIMマネージャーが必要だよね。日本の公民館とか、地方公共団体でそれをそれだけの役職を回すだけのプロジェクトがあるかなっていうのはちょっとわからないよね。
山上:規模で言ったら、そこに新たに人を一人を置くのは無理ですよね。
横関:そうすると、地方とかの小さな建築物、公共であっても、民間でもいいんですが、そういうものの建築自体をBIMが進化させるということは可能なんでしょうか。
東福:担当者の力量にもよるんじゃないの。結局つまらないこと言い出すとか。
山上:ということもありますが、逆に例えば変な言い方ですけど、大手組織設計事務所が地方で仕事をするとしたら、多分そういう人たちをはねのけて意見を通しやすくなるんじゃないでしょうか。
東福:なるほどね。
山上:僕では無理ですけど
恒川:発注形態とか設計者の選定の仕方とか。そっち側が変わらないことにはBIM自体が根付かない
東福:この前、JIAがプロポの要項自体を作って、実施されたじゃないですか。あれのBIM版みたいな可能性はありますね。
横関:今、2025年からBIMによる確認申請が可能になることになります。2027年からは、全面的にBIMによる確認申請がOKになって、少し状況が変わってくるかなと。その時が多分BIMの大きな普及が始まるタイミングなのかなと。
3、創造性をどう生み出していくのか。
横関:では創造性ということを考えています。今までの流れでどうしてもAIを省くことができなかったので、AIも含めてちょっと議論をしていきたいです。コンピューターが建物を理解できるような設計システムがこれから始まっていく時代に人間の最も特徴的である創造性をどう生み出していくか、もしくは拡張していくのかというところは、やはりすごい興味があると思うんです。一方で、そういうことをやることによって画一化されるんじゃないかと思われている方もいらっしゃるのではと思います。御意見を聞きたいと思います。
山上:どのくらい時間がかかるかは無視して考えると、まずツールからは自由になる方向だと思うんですよね。BIMどうこうじゃなくて、デジタル設計全般で誰でも環境シミュレーショできるし、簡単なものだったら構造屋さんなしでも構造設計できるかもしれない。ということを考えると、今は過渡期でそのソフトを使うのに四苦八苦している。理想的に進んでいけば、多分その設計者は判断することだけに、あるいはインプットすることだけに時間を使えるようになると思う。それは明るい未来だと思ってますけど、ただ時間がどれだけかかるか、それは、その一人一人にとっての問題なんです。
横関:誰でも環境シミュレーション、構造計算できる状態になった時に、創造性はどう変わるんでしょうか。
山上:ちょっと具体的な話をすると、例えばパラメーターはいろいろあるじゃないですか。究極的にはパラメーター自体がもう何万通りもあるはずなので、設計者がそれをチョイスして、それをもとに設計をするのは画一化よりもむしろ逆にもう、ものすごいバリエーションができてきますよね。
今よりもいろんなパラメーターを扱うことができて、しかもそれが根拠になるということなので、今よりも説得力のあるデザインというのが多分でき得るはずです。
横関:それはすごいですね。
山上:創造性がどう変わるっていうか、本当に可能性がすごくあると思うんです。これまでだったらめちゃくちゃ格好いいって思うけど格好良さの根拠は分からないという時代があって。
山上:例えば安藤忠雄だから、みんながオーダーしてくれる状況も多分あったんだと思うんです。それが僕みたいな一人で設計事務所をやってても巨匠レベルになれるかもしれない。根拠とかは全部出せるし、あとはだからみんながそれをどう評価してくれるかというのはありますが、創造性っていうのはわりと純粋になっていくと思います。
そうすると、今度、それ評価する方のいわゆる批評の世界がもしかしたら活発になるかもしれない。
東福:それこそAIが活躍するんじゃないの。
山上:形の根拠って今は、その環境とかエコも含めて、少なくとも日本人でみんなが理解できるのは機能的な話じゃないですか。それ以外のところの評価っていうのが、もう少し一般的になるといいなと感じます。
横関:例えば、ここにツマミが2つしかないという、ここをいじって何かを創造しろと言われるのと、たくさんツマミがあって色々やれるのでは違いますよね。パラメーターによって今までイメージできてないものに気がつくっていうことが多分できる。それが創造性を刺激していくのではないかというお話かなと。
山上:逆にどうにもならなくなっちゃうことも起きるかもしれません。
横関:多分そこは扱う人間の能力によりますね。
山上:そうですね。
横関:もう一つ面白かったのが、そこで出てきたものの根拠が示せるというお話。今までは何となく格好良いと感じていたものが、なぜ格好いいのか、なぜ効果があるのかということの根拠が示せる可能性が今出てきたと。
東福:でもそれはどうなんだろう。ツマミがたくさんある話で、その組み合わせ最適解を求めるのってコンピューターが一番得意とするものだし、AIって何がすごいかいうのはモヤモヤっとしたものを、なんとなくの傾向を示すことと思っている。要するに、すごいたくさんのパラメーターを同時に何10万と扱えるようになったっていうのはやっぱ大きい。なんか言語化できないものをもうAIは扱っちゃうんじゃない。根拠のないものの根拠を示せるっていう話だけど、根拠がないものを結構AIは作ってるよね今。画像生成系でも。
山下:画像生成系以外だと。
東福:ChatGPTもそうじゃない?根拠あるのももちろん得意だよね。だからと言って答えがあるわけじゃないんだけど、でも何か結構そういうのをブレークスルーしつつあるのが今の世界なのではないかと。
山上:そういうのってのは?
東福:根拠があるなしっていうのがもう無化されるっていう。何か知らないけど、これはAIが考えたものでいいものだっていう風な受け入れ方人間はしていっちゃうような時代が来ちゃうんじゃないかな。
横関:なぜAIのものがいいだろうという判断が下されるようになるんですか。
東福:確かにそうですねよね。たしかに、それはそうだね。私は建築情報学会も入ってますし、人工知能学会にも入っていて、人工知能が平面ずを描き始める日を楽しみにしてるんですけど、ただ、やっぱり全然できてないんですよね。建築AIベンチャーっていうのは結構あるんです。プランニングするとか。特にマンションの内装とか、区画のプランニングするとかの会社が結構あるそうですが、片っ端から撤退していってるみたいなんですね。今、日本には多分1社か2社しかベンチャーが残ってなくて、それのコンサルをやらないかみたいなのは一回誘いが来たんです。
それでAIを使ってやってるんだよっていうような話でホームページを見たらガチャガチャ動いてるんですよ。プランニングはできているんです。けど、これって遺伝的アルゴリズムじゃないのって言ったらその通りって感じで向こうがシュッて引いちゃったんですけど。要はそれって70年代の技術じゃないっていうような言い方をして。もちろんコンピューターが速いから早く動くようにはなってきているんですね。何かでも案外建築って難しいんだっていうことがAIやることになってもなっていて。
それから、もう一つの問題として、もうちょっと頑張れば建築AIみたいに出てくるんだろうけれども、それを開発するくらいだったら人間にやらしてた方が安いって判断もあるよね。すいません、変な話で。
横関:そこの話から創造性になにか結びつけれませんか。
東福:そうですね、たくさんツマミがあるとして、新しいツマミを1個作ることというのは、今のところ、多分人間にしかできない話で。それが創造かというと、新しいパラメーターを1個付け加えるっていうのがやっぱクリエーションなんだろうと思います。
山上:だけど、チャットGPTが提案をたくさんして、その中から選択して・・
東福:そう、最後選ぶんだよね。でも、ChatGPTほんとすごくて、ブレインストーミングとかは人いらなくなっちゃった。ずっと話してるだけで、ああそうだ!これがいいじゃんみたいなことができちゃう。まあ人間は介在するんだけど、みんなで集まってこう一つのパラメーターをひねり出すっていうよりは、AIと語らう中で、あっ!て思いつくっていうのはあるかもしれない。
横関:パラメーターを付け加えることが創造性じゃないか。いや、それすらもAIができる。だけど、そのAIをコントロールするのが人間だという。なんかぐるぐる回ってますよね。AIだけが勝手に何かをやってくれるってことはありえずに、やはり人間と両輪になってやっていくようなイメージにこれからなってくるのでしょうか。
東福:そうですよね。少なくともここ10年間くらいのトレンドはそれにならざるを得ないんでしょうね。チャットGPTの3.5/4.0が出た時は、お前どういう仕組みなの?っていう驚きがありました。私あのその画像生成系の時には、ちょっと色々なものの本を読んで理解しましたけど、論理的な文書を作るのはどうなっているんだろうっていうので、ずっとチャットGPTを質問攻めにして…
山上:やりました。でも3.5だったからあんまり。
東福:だから4.0買って、質問攻めにして聞いて。本当に凄い技術なんだけど、でもチャットGPTって、次の単語を予想するっていうタスクをずっとやり続けているだけなんですよね。学習から。要するに、「今日は雨です」の「雨」がない状態、「今日は」の後に次は「雨」という予想するというものが続いてて「です」とか、「。」とか、そういうようにして次の単語を予測するタスクをダーっとやってる訳です。そうすると1万ワードある文章だったら9万9999の問題ができると、それをひたすら解きまくっているという。それだけのシンプルな作業を繰り返している訳だけれど、多分チャットGPTのプログラム全部変えてもA4、3〜4枚分ぐらいだと思う。
山上:モデルの方がデータ多い?
東福:モデルの方がすごい。それは計算は電気代だけで多分3.5で4億円ぐらいかけてる。多分それでGPT4はその10倍ぐらいかけてるんだと思う。(スパーコンピューターの)富嶽を丸一日動かすこれ電力を掛けて計算をしていると。やってるタスクはすごい簡単なので、これだけの簡単なことであそこまでのものができるってのがすごい大発見だと思う。
横関:今、創造性が難しく高度のものなのってことが否定されかけてるような気がします。設計者が特別に持っている創造性だって言っていたものが、実は根源的な構造はシンプルなんじゃないかという疑いが出てきます。デジタル設計の中で創造性を生み出すということが実はすごい単純なアルゴリズムで生み出されてくる可能性。それを我々は選ぶだけという話に変わってくる。
東福さんが今まで経験してきて、設計に関わってきた経験値があります。私の経験値、山上さんの経験値、選ぶものが変わるはずですよね。目の前に並んでいても、同じものを選ぶとは限らない。可能性は幾らでもある。ただ、そこを最後決めなきゃいけない。この決めるっていうところに創造性の鍵が一つあるんじゃないかなと。そこについて何か議論していただきたい。
山上:結局、人間の創造性って全部外部化できないじゃないですか。一人一人の創造性が頭の中なので。だからブラックボックスですね。人間の中って。例えばファッションデザイナー、、、じゃなくてディレクターさん。いろんなブランドの良いものを見て、服を集めて服を組み合わせて、このモデルさんに着させるというその職業が結構な高給で成り立ってるってことは同じなんですかね。
設計者っていうのも、もし純粋な格好いい格好悪いみたいな話だけで言うんだったら、要は実務的なことはいらなくなって、その人の創造性は、結局組み合わせのセンスみたいな話になってきたら、それは多分その人のいろんな人がいろんなものを選ぶでしょうけど、デザイナー、設計者ABCがいてAの人はこういうコレクションを作りました。ファッションデザインでいうと、こういうコレクションを作りました。こういうモデルさんを集めて、こういう服を選んでこういうのをやりました。それがもうみんなに評価されるかどうかが実情。
そうするとその人の頭の中っていうのは、その人の個人なので、それはやっぱり外部化できなくて、いくらその人の選択を追跡してデータを積み上げたところで、その人はどんどん変わっていくので多分、永遠にそのデザイナーのクリエーションというものは失われない。
横関:なるほど。デザイナーのクリエーションって統一性がある。例えば、安藤忠雄が作る建物っていうと、なんとなく見ると分かりますよね。ファッションデザイナーもそうです。ある程度の統一性を持っているのって、それはなにか可能性を制限していることになりますか?
山上:それは90年代とかに、当時若かった塚本さん達が「空間から状況へ」という展覧会ありましたよね。その頃の議論でありましたよね。安藤忠雄さんのように作風を確立してやっていくっていう人でもあるんだけど、それ以降の人たちというのは、作風でやるんじゃなくて状況を作るんだとかっていう議論が既にされている。
東福:なんとなくでラインがあるわけだから。
山上:例えば、平田晃久さんなんかは作風を作ろうとしてますよね。けど、それを目指さない人が今たくさんいるいるじゃないですか。実際。
東福:どうなんだろう。作風は造りたいんじゃない?
というか要は例えばお金持ちの世界ならカタログ化しなきゃいけないみたいなのが当然あるわけで、安藤忠雄に木造の建物作ってほしくないわけだよね。安藤忠雄に頼むんだったら。打ち放しを欲しいし、ザハ・ハディドに真四角の建物が建ててほしくない。そんなようなもので、やっぱり建築家というのはある程度だったらやってくんじゃないのかな。
山上:求められるものを出していくっていう。
東福:きっとそれはもうクリエーションではない。
山上:そこから脱却しようと自覚的に動いている人がいるっていうのが僕の認識です。実際できているかどうかっていうのはいろいろあると思いますけど。
横関:創造性の問題は、建築家として認められるかどうかっていう話はまた別?
東福:全然違う話ですね。
山上:売る方法としては分かりやすい方がいい。
横関:戦略としてのイメージなのか、純粋なクリエーションなのかというのが見抜くことが難しい。
東福:純粋なクリエーションって逆にどういったものか。それが一番の問題ですよね
横関:それが先程の話に戻るのかなと思っていて。
東福:選ぶって話になるかっていう話ですよね。過去のものであったりして、過去のものから何を選ぶかっていうのがクリエーションだというのはある話ですね。
横関:昔、芸術家の人に、自分自身の特性がわからない時、あらゆる情報を集めてみる。何も考えずにただ直感で。それを並べて俯瞰した時に自分の特性がわかるって言われたんです。 そのくらい実は単純なところで選択はされているのではないか。
山上:やっていることは単純に見えますが、人間の頭の中で行われていることですよね。インプットとアウトプットは自覚的じゃなくても複雑なことが行われてるんじゃないかなっていうのが、私がイメージしている個人のクリエーションですね。それがもっとシンプルにできるようになるといいですねっていう話ですけど。実際に実務の労を伴わずに。
4、社会とどう接続させるのか。
横関:この議論、今日話した内容が実際の社会と接続して、社会を良くしていくにはどうしたらいいか。たというところについて、御意見をいただきたい。
山上:BIMがということなんですね。
横関:できればデジタル設計全体で。例えばGRASSHOPPERがあれば、いろいろ面白い形を作ったり出来ます。ただ実際社会の中に出てくることは少ない。社会を変えていく、インパクトを与えていくにはどうしたらいいか。
山上:そういう言い方をされるとデジハブになっちゃいますけど。
東福:いや、まあそういうような話もあるけど、グラスホッパーを教えてるって言うと何であんなもん教えるんだと。あんなのコストがかかるような形が出てくるだけじゃないかという言い方を良くされるんです。けど、そういうふうに言ってる人こそ実際に使ってほしいわけですね。コスト感覚と分かるのであれば、それを実装すればいいじゃないと思うわけで。BIMでもグラスホッパーでもプログラミングでも。案外そんな難しくないと思うんですよね。
横関:コストコントロールができるというんだったら使ってみて。
東福:そう、そうすれば、その人のコスト感覚が全部実装されるわけですよね。
横関:それがまさに社会と接続する。
東福:実際、それができると思うんですよね。グラスホッパーで。
山上:実際やられてると思うんです。複雑じゃないですけど、その竹中工務店が3Dボロノイの建物をもう既に作り上げている。
東福:やりたかったんだろうなという形ですよね。
山上:竹中の多分、1次下請けの鉄骨屋さんさんとかだったから。竹中もやりたいし、鉄骨屋さんも、いろんな人がやりたかったからできてる。みんながそう思っていればできちゃうんですよ、お金多少かかってもいいんだから。
横関:山上さんからも、こういう風に接続させればいいのにというのがあれば。
山上:やっぱりもう実践ですよね。さっきのデザイナーの頭の中がストレスなく形にできるようになるには、まずもっと技術発展しないといけないので、グラスホッパーだってやっぱり難しいと言えば難しいし、BIMだって難しいと言えば難しいですけど、恐らくそれを使っていって、だんだんしか改良はできないので。
建築設計やってれば、元々何らかの社会に繋がりはあるので、BIM使って設計をすれば間接的には何か反映はされるはずですし、とにかくもうやるということじゃないですか。それこそ文句を言ってる人に対しては別にやったらっていうだけです。やらないと進んでいかないので。
僕はARCHICADがまあまあできるのですが、ARCHICADが直接なんかめちゃくちゃいい設計をするとは当然思ってないですし、 めちゃめちゃ使いにくいとこたくさんありますし、だけどそれを使っていかないとその先はないので。
横関:要は難しいから今ハードルがあるだけの話で、これがすごく簡単に使えるのであれば、誰もがシミュレーションができる、コストコントロールができる、新しいクリエーションができるようになる。この結論って一番最初の方でちょっと出てたと思うんですけれど、難しいことが問題であって難しさがなくなることで、一気に新しい何か設計が始まるように聞こえますね。そうするとそこを誰かが変えてくれれば。
山上:でもそこなんですよ。その誰かが変えるというのがないので。で誰か一人が全てのソフトを劇的に使いやすくしてくれるなんてことはないので、それは僕たちが使ってメーカーに文句を言って、だんだん変えていく、改善していくしかないですね。ソフトの話でいうと。
横関:ありがとうございます。
では、最後にBIMでしか設計をしたことがないような、BIMネイティブな時代が始まると思うのですが、これからBIM、デジタル設計が本格的になる世界に飛び込もうとしている若い人たちに一言何かメッセージがあればお願いします。
東福:私が思うのは、BIM的なBIMってすごい良い子ちゃんなソフトだと思うんで。Vectorworksの前身のMiniCADの時代からもう壁が自動で建って、窓張り付いてっていうのはあったんですよね。当然、自動的に2本線が引かれて、自動的に窓パンってついてっていうのがいいなと思うのは誰しも当然で。そういうような正常な進化を遂げてきた中に、今のBIMというのはあると思うのですが、それが逆にBIMのソフトウエアが全くワクワクしないものになっちゃっている。ワクワクしないのが問題だというのはずっと聞かされているんです。
なんかもっと西海岸辺りからそういうのを超えるワクワクするソフトが出てきたら、この世界はカーンと変わるので。もっと柔らかいスタンスでいった方がいいんじゃないかなとは思います。
山上:僕は途中まで立場同じですけど、最後逆ですね。
東福:これ何か東海岸的にはつまんない。
山上:いや、だからいや基本。こういう、
東福:なんで右上に家の形くるくる回して扱わなきゃいけない。
山上:それは僕も思います。結局BIMってのはやっぱり効率の求めるものなんですよ。効率求めるのはつまらない。
東福:だけど、それは学問的話であって、やっぱ物事を分けて区別して分けていくっていうのが学問のあり方。これだけ色々な分野がモヤモヤとしたものをモヤモヤとしたまま扱えるようなプラットフォームが整えられている中で、何でこんなに分けなきゃいけないのっていうのは。
山上:だから効率化ですよ。
東福:効率。それが効率化だっていうのがちょっと考え方が古いんじゃないのって思うんだよ。
山上:いやいやいやいや。
東福:いやそれはそう。だからそういう人っていうのはだいたいこう南方熊楠とか大好きなんだよ。分類学者がね。
山上:いや、そういう話じゃなくて、、、
東福:全体的にはふわっとしたものをふわっとした感じで扱えるような世界が整えられてきているのに、なんかやっぱりBIMは気に入らんっていう。
横関:今のワクワクしないBIMはつまらない。
東福:そうですよね。
山上:モヤっとしたものをモヤっとしたまま伝えるってことは、結局人間がしている判断をもっとコンピューターができるようになってほしいということですかね。
東福:なんか最初にコンピューターゲームが出てきた時のようなこう西海岸的なワクワク感が一切ないっていうのはBIMの嫌いなところの一つ。笑
山上:一応、ちょっと東福さんはもう分かってるかもしれないですけど、もう一回言いますね。
東福:いつもこれで喧嘩になる。
山上:効率を求めるってことは、要は自動化なので、人間が判断しなくてもいいことを勝手にコンピュータがやってくれるっていうのが、BIMが画一的になっていく理由ですよね。スタンダードな建物の作り方だとこうだよねってのを勝手にやってくれるから人間はその分労力は減る。
それが意図してることと違うと設計やる人はムキーってなっちゃうというのが今の話のベースですよね。だから僕は今のところBIMは、ある見方をすればつまらないっていうのはそれはそうかなっていう気がするんです。
で、大学でBIMを教えなくてもいいって僕が言っているのもそういうことなので、思考回路がもう決まっちゃうんですね。BIMって。だって効率化してるんだから。東福さんが言っているような未来の効率化ってのはちょっと置いといて、現時点での技術での効率化っていうのはそういうことなんですよ。だから思考がそれによって狭められちゃうっていうかレールが敷かれちゃう。 だからBIMよくないなという話になっちゃう。だからこれからのBIMネイティブの人に言いたいことはBIM信じるなとかやっぱりそういうことになりますよね。手で考えろとか、そういう話になっちゃうもしくはライノを使えと。
横関:BIMで思考が狭まらないようにやりなさい、狭まることに自覚的であれと?
山上:でもBIMで思考思考が狭まることに自覚的であれって言っても、そんなの無理なので。
東福:効率化っていうのを求めるっていうことは画一化していくことではあるとは思う。
山上:現時点での技術レベルの話をしているんです。それはそのChatGPT的なふわっとしたやり取りが近々できるようになるかもしれないねってことを僕は否定してるわけではないですよ。
東福:そんなに逆方向のこと言ってるわけではないけれど。もともと建築なんて床と柱と壁を作って屋根作って、面積作る職業じゃないですか。だからそんなに難しい話じゃないんでね。しかも1Gみたいな、それぐらいのその程度の重力しか働いていないんで、そんなに大した話ではないんじゃないのって思ってる。
ただ、そういう風にして脱構築論者たちが柱でも床でも屋根でもないものっていうのを定義し続けたのがデコン(ストラクション=脱構築)の運動だったわけで、それが全部無かっことになって、でやっぱり柱壁屋根で全部を入力していかないといけないというのが、むかつくところだよね。
山上:でもそれはライノと連携してできます。ARCHICADとグラスホッパーで連携して、グラスホッパーの方で作った形をARCHICADに戻してそれをそのまま図面としてできますから。まあそれをすぐやるのは難しい。トップレベルですけど、
横関:BIMへの不満などそれはそれで興味深いです。まだまだお聞きしたいのですが時間を大幅にオーバーをしてしまっているのでこの辺りで。今回も非常に内容の濃いものになりました。どうも今日は長い時間ありがとうございました。
一同:ありがとうございました。
Prev:BIMが切り開く新たな創造性 第5回〜 村井一建築設計/東京大学生産技術研究所 特任助教 村井一氏インタビュー〜
第1回:BIMが切り開く新たな創造性 第1回〜プロローグ〜
第2回:BIMが切り開く新たな創造性 第2回〜広島工大 杉田宗氏インタビュー〜
第3回:BIMが切り開く新たな創造性 第3回〜日建設計 芦田智之氏インタビュー〜
第4回:BIMが切り開く新たな創造性 第4回〜久米設計 古川智之氏インタビュー〜
第5回:BIMが切り開く新たな創造性 第5回〜 村井一建築設計/東京大学生産技術研究所 特任助教 村井一氏インタビュー〜
第6回:BIMが切り開く新たな創造性 第6回(最終回)〜零三工作室 東福大輔、山上建築設計 山上健 座談会〜